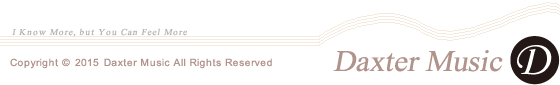和音の転回
前回はハイドンの合唱曲を聴きながら、見慣れた和音の配置を、ワイドレンジに四声部に振り分ける開離配置について学びました。その際に密集配置(アレンジ)の譜面をお見せしましたが、所々で今まで学習してきた形と違う和音の存在に気づかれたことでしょう。
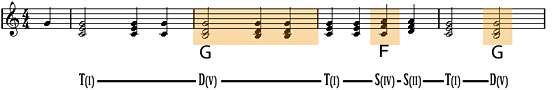
ハイドン「天地創造」合唱部の密集配置(アレンジ)
ドミナント(V)はGメジャーコードになりますので、皆さんが知っているG・B・D(ソ・シ・レ)という音の並びとの相違から疑問を持たれたのではないかと思います。実はこれは転回形和音と言って、和音の構成音のうちの第三音や第五音が最低音に配置された形になっていたのです。
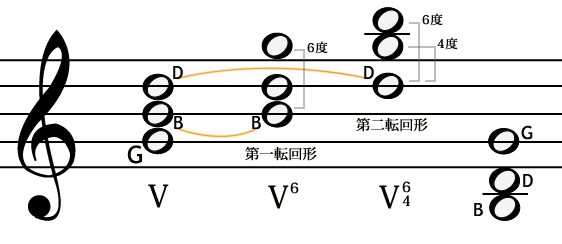
第一、第二転回形の一例
(通常は最低音がバス部に配置されたりと、高音部のみで構成されることは少ないですが、あくまで視覚的理解のために譜面として示します)
第一転回形は第3音を最低音に配置した転回形で、主音までの音程(6度)から六の和音とも呼ばれています。第二転回形は第5音を最低音に配置した転回形で、主音までの音程(4度)と第3音までの音程(6度)から四六の和音とも呼ばれています。ハイドン「天地創造」(アレンジ)のドミナント(V)は上図右端の(1オクターブ下がった)第一転回形、サブドミナント(IV)のFは第二転回形に該当します。
四声体(上三声+バス部)の転回形
作曲の基本となる四声体の転回形も見ていきましょう。前頁でも説明しましたように四声体では和音を開離させながら各声部に構成音を振り分けます。下図はトニック(Cメジャー 構成音:ドミソ・CEG)における、基本形、第一転回形、第二転回形になります。楽典における転回形の定義は最低音を基準にしていますので、バスの音によって転回の扱いそのものが変化します。左から順に、主音であるC音が最低(バス)音である基本形、3音であるE音が最低(バス)音である第一転回形、5音であるG音が最低(バス)音である第二転回形になります。
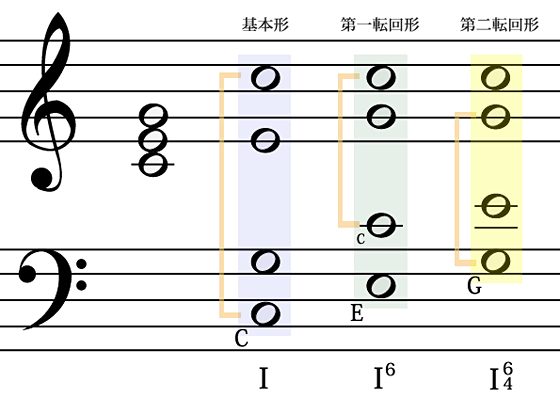
上三声とバスを合わせた基本形と第一、第二転回形
三和音を四声部に振り分けるのですから、重複音が生まれます。基本形では根音、第一転回形も根音(機能的に弱まりますが第五音も可)を重複させるのが一般的です。第五音を重複させることが多い第二転回形はドミナント前で使われることが多いのですが、基本形からドミナントへ移行した時の聴こえ方と、第二転回形からドミナントへ移行した時の聴こえ方を比べながら、その理由を探ってみましょう。(少々聴き取りにくいと思いますが、なるほどと分かった時は知識になります。しかもこの感覚というのは作曲の肝でもあります)
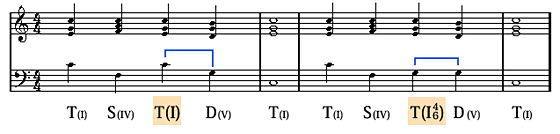
基本形と第二転回形によるドミナントへの連結
いかがでしたでしょうか。環境によっては聴き取りにくかったかもしれませんが、正格カデンツ(T-D-T)において、ドミナント前の強拍部にあらわれる(トニックの)四六の和音は終止の四六と呼ばれます。トニックの第二転回形における最低音(第5音)と、ドミナントの主音が同じ音になることで連結機能が強まるため、その連結は柔らかく自然で、キザキザ型の基本形よりも耳にしっくりくるのです。セブンスやテンションを用いる際のボイシング(構成音の配置方法)も、基本的にはこのようにスムースな連結を心掛けながら行います。
ちなみに第二転回形にはこの終止の四六のほか、経過の四六、補助音の四六、停留音の四六、後打の四六などがありますが、それらは非和声的、装飾的なものになります。全てをなめらかにしては退屈になってしまう曲もあれば、良い曲もあります。ドッシリと構えた基本形から、第一、第二転回形と、時に応じて使い分けていきましょう。
人気コンテンツ daxter-music.jp
人気コンテンツ daxter-music.jp