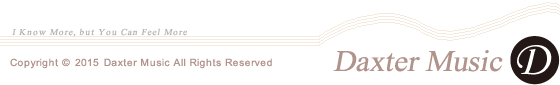すでに作曲ができる
さて、ここまでは前書きにはじまり、11種類の和音、主要三和音と副三和音による和音の機能性、その進行と終止の基本形であるカデンツ、音楽を四つのパートから考える四声部、および和音の転回形を学んできましたが、おおむね和声学の基本は終了になります。この後も様々な知識を身につけながら応用や実践に進みますが、ここまでの知識があればハイドンの天地創造の合唱部のような素晴らしい曲が作れるということになります。
楽典マジックと申せましょうか、当たり前のことでも、それが譜面になり記号化すると気が滅入るような圧迫感を受けることもあるでしょう。退屈が続けば「やっぱり音楽やめた!」なんてことにも繋がりかねませんが、学問と実践は少し距離があるものですので、あまり詰め込みすぎず、少しずつ覚えていけば良いでしょう。
むしろ前6ページをひと通り学んだら、机上の学問はストップして、三和音(ドミソやソシレ)を上手く組み合わせながら、自作曲の構成を磨く訓練をしていきましょう。ハイドンのようなレベルに到達するのは難しいかもしれませんが、音楽は「音出してナンボ、曲作ってナンボ」の世界だと思います。あの珠玉の「新世界交響曲」で知られるドヴォルザークは、楽典的に改善の余地のある作曲家に対しても間違いは指摘せず、「あれで良いのだよ」とお弟子さんを諭されたそうです。
巨匠たちこそ学んだ
相反しますが、やはり学問も大切です。ハイドンもモーツァルトもベートーベンもブラームスも、みな共に苦学の時代がありました。掛留音や先取音を巧みに操り、従来の和声に危機をもたらしたとも言われるワーグナーですら、10代の終わりには和声学をしっかりと学んでいるのです。直後に彼が残した、生涯でたった1曲の交響曲からは、古典派や調性音楽への帰順を感じます。古典的な作曲家としての評価はさておき、あの勇壮で美しい旋律の下地には、先人たちの知恵があったとも言えるでしょう。
ですから、インプットとアウトプットのバランスが大切ですね。基本を学び終えたのですから、先ずは思うがままに2、3曲でも作ってみましょう。ひとつアドバイスがあるとすれば、初心者はピアノなどで全音符を並べてそれをバッキングにし、そこにメロディをつけていくといった作曲方法に集中してしまい、無味乾燥でつまらないものとなってしまう場合があります。そんな時は音階と調を勉強してから(全て理解しなくても良いです)、実践基礎:スケール編に進むのも良いでしょう。モード、音階(スケール)、調性、コード(和声)の相関性が、歴史的にも理論的にも深まるので作曲能力が向上すると思います。次ページからのセブンスやテンションにしても音階(スケール)上に存在するものなので、和声学というセクションのみで学ぶと身につかないかもしれません。
人気コンテンツ daxter-music.jp
人気コンテンツ daxter-music.jp