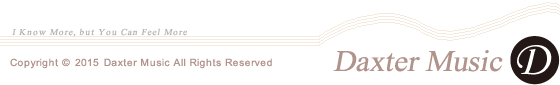奏法を知ろう
ベートーベンは弟子のチェルニーに「モーツァルトの演奏は見事であったが、ポツポツと音を刻むようでレガートではなかった」と語ったと言われています。モーツァルトの演奏を聴いていたベートーベンは当時まだ17歳でしたが、皆さんはレガートという奏法・表現方法をご存知でしょうか。
楽器を知るということはその構造や奏法を知ることです。第1回~第4回までは独断かつシンプルに(クラシックの)主要楽器の説明をしてきましたが、このページでは菊池有恒先生(一部に山縣茂太郎先生)の楽典本から引用する形で、奏法(アーティキュレーション)について紹介してみたいと思います。
| legato レガート |
音の間を切れ目なく、なめらかに奏することで、その部分はスラーによってあらわされる。スタッカートの対義語 |
|---|---|
| staccato スタッカート |
音と音を切り離して奏する。あくまで感覚的ではあるが、無印のスタッカートはおよそ1/2の長さで、staccatissimoは1/4、mezzo staccatoは3/4で奏する |
| slur スラー |
多義があるが、弦楽器の曲にスラーがつけられた場合は、同じ方向に一弓で奏するbowing(運弓法)を指す。声楽、管楽器では一息で、木管楽器ではその間にタンギング(舌の運動で空気の流れを中断する)しないことを示す |
| portamento ポルタメント |
高さの異なる2音間を非常になめらかに奏することで、声楽、擦弦楽器、トロンボーンなどでは効果的に使われる |
| tenuto テヌート |
いくらかのアクセントをつけ、音を豊かに響かせるために音符の長さをいっぱいに延ばす |
| tremolo トレモロ |
一つの音の急速な反復で震えるような音を出す |
| attack アタック |
音の出だしを明確に始めること |
| pizzicato ピチカート |
弦を指ではじく奏法 |
| arco アルコ |
弓の意。(ピチカートなどを止めて)弓で奏すること |
| flageolet フラジョレット |
ハーモニクス(倍音奏法)の意、たとえば弦を指で軽く押さえ弓でこすることで得られる |
| glissando グリッサンド |
順次進行ですべらすように急速に奏する |
| Pedal ペダル |
ピアノ、ハープ、ティンパニ、チェレスタなどの楽器で足を使って奏する |
先生の著作に「アーティキュレーションとは音と音との切り方や結び方に関する処理の方法と、それをささえるためのテクニックのありかたをいう。つまり、フレーズに至る以前の、言葉にたとえれば、単語にあたるごく小さな単位の演奏や表現に関する奏法のあり方をいう」とあります。
ポルタメントは中国の楽器である二胡の音が印象的です。弦に油をたっぷり含ませてヴィィーンと情感にあふれた音を奏でます。前述のように金管楽器でも効果的な音が出せるようです。アーティキュレーションは楽器の構造にも大きく影響されますので、一概に音の特徴を語るのは難しいとも言えます。たとえば、ギターとヴァイオリンの倍音奏法の音では趣が大きく異なります。
奏法の選択は、音のデュナーミク(強弱)を表すmp、mfなどの指示記号や、Allegro、Moderatoなど速度を表す標語、dolce cantabileなどの曲想を表す標語を通じても行われます。三重奏や四重奏ではきわめて繊細な音が要求されるケースも多いですから、曲の理解者が音の長さと必要とされる音勢を見極めて、直接的に奏法を指示していくことも大切です。
legato レガートという奏法について
奏法の特徴を学ぶと、冒頭のベートーベンのコメントも何となく理解が可能になります。モーツァルトの曲調ならスタッカートが最適だ!と考えるのも間違いでは無いでしょうし、感情表現の甘さをベートーベンは指摘したのだ!と想像してみるのも面白いです。そのレガートに関しては、以下のようにたくさんの種類がありますので、もう少し学んでみましょう。
| legatissimo レガティッシモ |
前の音符と次の音符が少し重なるような感じで奏される。molto legatoは前述のportamento(ポルタメント)と同義 |
|---|---|
| molto legato モルト レガート |
|
| legato assai レガート アッサイ |
|
| poco legato ポコ レガート |
legatoとstaccatoの中間的な奏法、スラーとスタッカートで記譜されるが、たとえば弦楽器においては、同一方向の弓で断奏することを表したスタッカートの奏法(ポルタート奏法)である |
| un poco legato ウン ポコ レガート |
|
| legato non tanto レガート ノン タント |
|
| non legato ノン レガート |
legatoで奏さないことを示す |
| mezzo legato メッゾ レガート |
legatoとstaccatoの中間的な奏法であるが、ピアノの演奏では独特の打鍵法を指示する用語になる。鍵盤を打って力強い音で奏することを意味し、音量を増大する際に用いられる |
| legato staccato レガート スタッカート |
感情を前面に出すような奏法もありますし、比較的無機質な奏法もあるでしょう。それを支える技術はもちろんですが、音楽は音そのものであり、名士はまた感覚的、感情的にそれを良く奏でます。「常に本質のみを聴け」と語ったベートーベンのレガートも、本質たる古典派の和音にのった彼の話法の一部であったのでしょう。
人気コンテンツ daxter-music.jp
人気コンテンツ daxter-music.jp