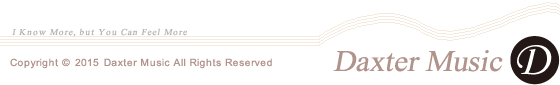関係代名詞のwho
うちの姪っ子のママのお父さんといえば自分の父親のことですが、物事の説明というのはしばしばややこしくなりますので、それを英語で表現するとなると大変です。そんな時は関係代名詞の出番です。先ずは一番有名なwhoを使った例文をみてみましょう。
Carlos Kleiber is a conductor who is well known for his masterful performance of Brahms's symphony No.4.
カルロス・クライバーはブラームスの交響曲第4番の名演で知られる指揮者です。
人物にはwhoを用いて英作文を行います。関係代名詞のwhoが主語であるCarlos Kleiberにかかり、長めの文をスマートにしてくれます。
関係詞が入るべき箇所の後が不完全な文には関係代名詞をあてる。
今回の例文ではwhoが主語の役目をしているので当然ですが、whoの後の文に注目すると主語(名詞)が欠けていることに気付くはずです。以下の表のように、関係詞の後ろが不完全な文には関係代名詞を、関係詞の後ろが完全な文には関係副詞を用いて前後を接続すると覚えてください。
| 種類 | 語 | 関係詞節の特徴 |
|---|---|---|
| 関係代名詞 | who | |
| whose | ||
| whom | ||
| which | ||
| 関係副詞 | where | |
| when | ||
| why |
関係詞節が不完全な時、名詞の代わりをしながら先行詞(ここではa conductor)と関係詞節を接続させる役割を担うことから、関係代名詞と呼ばれています。
関係代名詞のwhose
続いてはwhoseです。(関係代名詞の文法的な働きは説明しましたので後は気楽にいきましょう。)
He has a brother whose name is Carl.
彼にはカールという名前の弟がいる。
whoseの後は名詞がくる。whoとwhoseは主語にかかる
whoseも後ろの名詞と協力して、whoと同様に主語の機能を担うで見極めはそう難しくありません。
関係代名詞のwhom
さて次のwhomは少々難しい関係代名詞です。
Telemann is a composer whom you may not know.
テレマンは君が知らないであろう作曲家です。
whomは目的語の働きをする。省略も可能。
この文ではknowの目的語がないことに注目です。このようなケースではwhomを用います。ピンとこない人は文型を復習しましょう。
You know Telemann.
あなたはテレマンを知っている。
上記は典型的な第3文型ですが、前述のwhomがTelemannと密接な関係にあることが分かります。このパターンは無数に存在しますのでwhomもそれだけ使われるということです。また省略も可能ですので、文中には現れませんが文法的には存在しているともいえます。
関係代名詞のwhich
次は人物ではなく事物を修飾する関係代名詞をみていきましょう。
The violin is a musical instrument which is made of spruce and maple.
バイオリンは松や楓で作られる楽器です。
whichは人以外のものを修飾する。
whoは人を、whichはものをという基本は覚えておきましょう。
さて、詰め込みすぎはよくありません。詳細は別途解説するとして、今回はここまでにしておきましょう。
人気コンテンツ daxter-music.jp